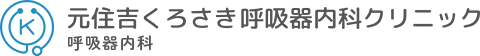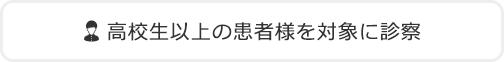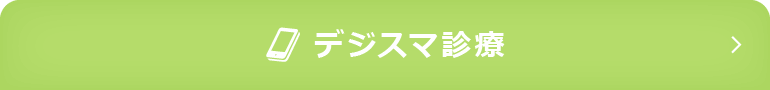予防接種とは
 近年日本国民の過半数が受けている新型コロナワクチンの接種に代表されるように予防接種とは特定の感染症による病気の予防のためにワクチンを接種することです。
近年日本国民の過半数が受けている新型コロナワクチンの接種に代表されるように予防接種とは特定の感染症による病気の予防のためにワクチンを接種することです。
予防接種を受けることでその病気の発症によるダメージを予防、または防ぐことが可能です。
インフルエンザワクチン
インフルエンザワクチン
 インフルエンザワクチンの予防接種を行うことで感染や発症そのものを完全には防御できませんが、インフルエンザによる重篤な合併症及び死亡を予防し患者様のダメージを最小限にとどめることを期待して行います。
インフルエンザワクチンの予防接種を行うことで感染や発症そのものを完全には防御できませんが、インフルエンザによる重篤な合併症及び死亡を予防し患者様のダメージを最小限にとどめることを期待して行います。
このワクチンの効果は、年齢、本人の体力、ワクチンに含まれている株とそのシーズンのインフルエンザの流行株との合致状況によっても変わります。
65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったという報告があります。
みなさまが毎年接種している日本のインフルエンザワクチンでもWHOが推奨したウィルス株を基本にして、日本の流行状況や健常人の持っている免疫の状況を見ながら予測して作られています。
私も高齢者や持病をもった患者様などには毎年必ず接種するようアドバイスをしております。
肺炎球菌ワクチン(R7より公費での肺炎球菌ワクチン接種の対応ができません。自費のニューモバックスのみ可能です。)
肺炎球菌は肺炎の原因菌の中でも特に毒性の強い菌です。
肺炎のほかにも
- 副鼻腔炎
- 中耳炎
- 髄膜炎
- 関節炎
- 敗血症
を引き起こすことが知られており、数時間のうちに急激に状態が悪化してしまう患者様も実際におります。
肺炎球菌は莢膜というバリアーを持っており、その型により90種類以上のタイプが知られております。
よく患者様より「一度肺炎球菌性肺炎を起こしたのでもうワクチンは不要なのでは?」と質問されることがありますが上記のように90種類のタイプが存在しており、今後も他のタイプの肺炎球菌性肺炎を起こすリスクは十分にあります。
なので適応のあるかたには是非ワクチンをおすすめいたします。
また、肺炎球菌ワクチンにそのものに菌が入っているわけではありませんのでワクチン接種によって肺炎になる可能性もありません。
ワクチンの副反応としては20-30%の人に下記の副反応が起こることがありますがほとんど問題にならない程度です。
- 微熱
- 注射部位発赤・疼痛・腫脹
- 頭痛
上記などの反応はインフルエンザワクチンでも起こる反応と同じですので過剰に心配する必要はないですが、アナフィラキシーなど重篤な副反応が疑われるような場合は速やかに医療機関の受診をお願いいたします。
肺炎球菌ワクチンの種類は2種類あります。
- ニューモバックス
- プレベナー13(13種類に対応)
ニューモバックスは日本では1988年に承認となったワクチンで65歳以上もしくは2歳以上で免疫力が低下する疾患をもっているかたが対象です。
23種類の菌のタイプに対応しています。公費接種がみとめられており、65歳以上で5の倍数の年齢になるかたが対象(公費接種は1回の接種のみが適応で、以後は自費になります)で、 一方プレベナー13ですが日本では2014年に65歳以上の成人に対しての承認されたワクチンです。
7種類タイプのワクチンは以前から乳幼児用として使用されておりましたが現在は乳幼児も13種類タイプへ変更となっています。
13種類の中にはニューモバックスに含まれていない種類のものも含むため2種類のワクチンを打つことで相乗効果が狙えることになります。
プレベナー13はまだ公費の対象になっていませんので自費での接種になります。
2種類のワクチンを接種する場合一定期間の間隔を空ける必要が出てきます。
公費の対象となっているニューモバックスを受けるタイミングをもとに接種のスケジュールを決めるとよいでしょう。
肺炎球菌ワクチンを特におすすめする人
肺気腫(COPD)、糖尿病、喫煙者、高齢者、心疾患、腎不全、肝疾患、血液の悪性腫瘍、脾臓を摘出したかたは感染するリスクが高いため接種をおすすめいたします。
肺炎球菌ワクチンの通知がきた皆さんにはワクチンを受けることをおすすめいたします。
肺炎の予防には肺炎球菌ワクチンだけでは十分ではありません。
肺炎球菌ワクチンは肺炎球菌という菌のみに対するワクチンです。
肺炎を起こす菌はほかにもいくつもあります。
基本的なこととして手洗い、うがい、口腔内の清潔を保つこと、規則的な生活、バランスのとれた食事など健康的な生活習慣の維持が何より大切です。
「予防は治療に勝る」という原則にのっとり前向きに検討していただけますと幸いです。
ご希望のかたは事前にお問い合わせください。